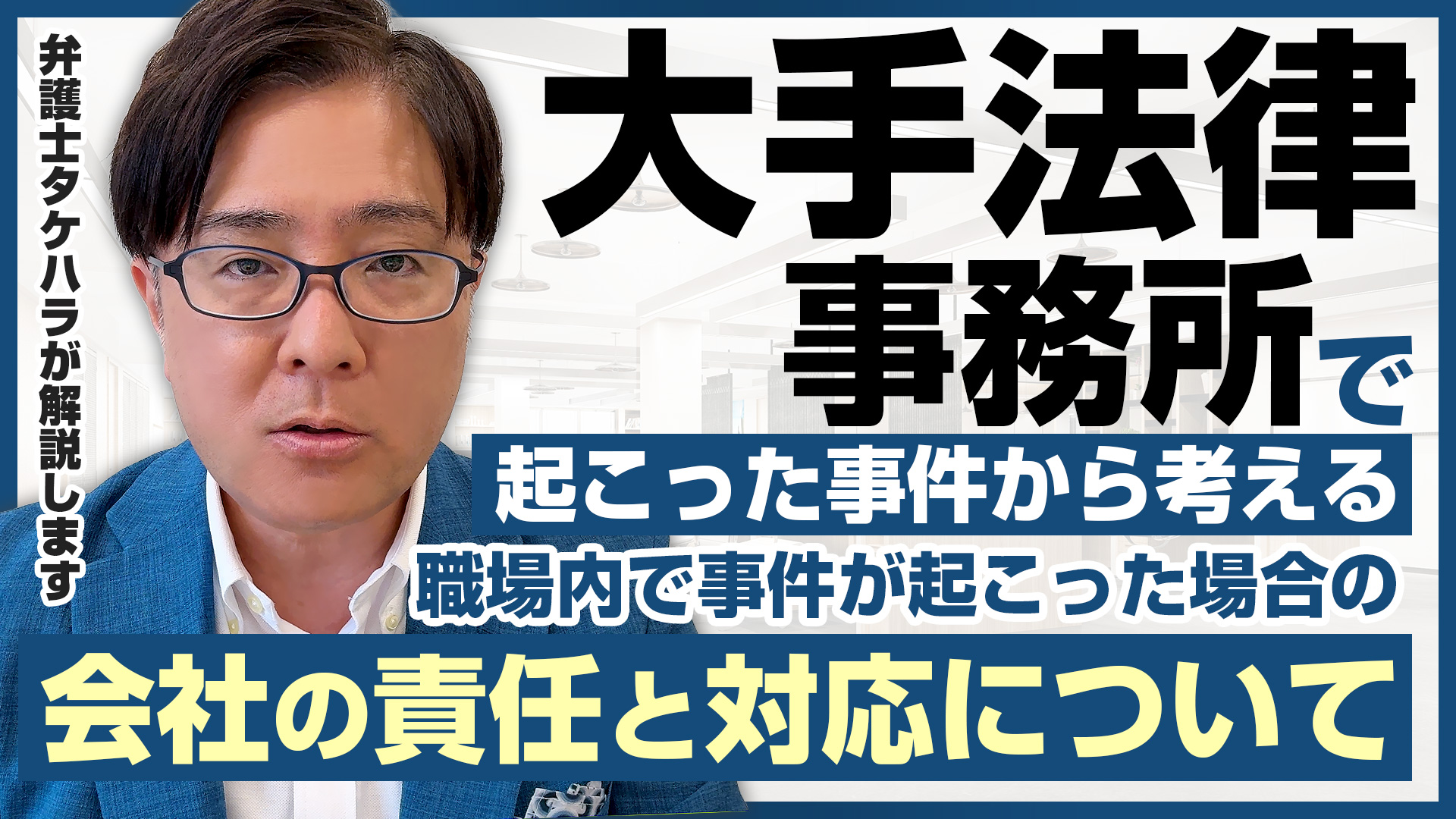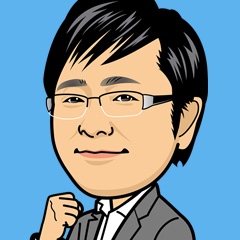本当のところどうなのという皆様の疑問にお答えしていくブログです。
できればブログ内の動画の方をご覧ください。
弁護士の嵩原安三郎です。
先日、某大手有名法律事務所の同僚同士が、加害者と被害者になる〇人事件が発生し、本当に衝撃を受けました。
弁護士はね、僕らの仕事って恨みを買いやすい仕事じゃないですか。
うまくいけば相手方から恨みを持たれるかもしれないし、あまりうまくいかなかったってことになると、その依頼者から恨みを持たれるかもしれない。
だから、僕らってどこかで
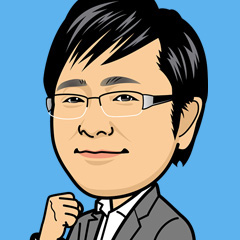
何かあったら身を守らないといけない
ということを覚悟しながら仕事をしている。
でも、事務員さんは関係ないじゃないですか。
だから、事務局員が被害者になる事件というのは、あまり想定はしていないのね。
だけど、これ実際に会社内で起こる〇人事件を改めて調べてみますとね、時折起こっているんですね。
例えば、自分が業務的なことでぶつかった、その相手が相手のことについて恨みを持っている中で、その相手がですね、自分が気になっている女性とも仲良く話しているということで、恨みが募っていき、〇人事件に至ってしまった。
そういうような事件だったりとか、同僚同士なのかな、そのトラブルになっているところに仲裁に入ったこの人に対して、その仲裁の仕方がよくないってことで恨みに思って、〇人事件に発展。
夜中、電話口で「わーっ」と口論しててですね、もうカーッとなったんでしょうね。
それで、その相手の被害者のところに行って、ナイフで何回も滅多刺しにして〇害してしまう。
そういうような事件というのが、報告されているんですけれども。
そういうのを見ているとですね、懲役十七年とか十八年とか十九年とか、割と重い。
でも、皆さんから言うと「無期懲役とか〇刑じゃないの?」って思うかもしれないから、重いのかどうかっていうのは本当に議論はあるかもしれないけども、そういうような事件というのはあります。
今回もね、このような職場内で事件が起こった場合に、本人だけじゃなくて、その社長だったり会社だったりが「責任を負うのか?」、それと、今回のような事件があった時に「どのようなところに着目して捜査が進んでいくのか?」「どういうところが問題になるのか?」ということ。
そして最後に、このような事件、防ぐことは不可能かもしれないけれども、会社側、企業側、あるいは事務所側で「どんな努力ができるのか?」ということ。
これ等について、お話ししていこうと思ってます。
職場内での事件と法的責任
まずね、職場内かどうかに関わらず、こういう事件が起きましたっていう時に、この加害者が責任を負うのは、これは当然だと思うんですね。
じゃあ問題は、会社内で起こってるんで、社長とかその会社、法人がね「責任を負うのか?」という問題。
この場合の責任っていうのは、二つに分けないといけなくて。
一つは「刑事責任」。
刑事責任というのは、会社内で事件が起きた場合に責任者が問われる問題、「刑事責任」。
皆さんもご存じのとおり、「懲役何年です」とか「無期懲役です」とか「〇刑です」のような、罪を償うための責任。
もう一つは「民事的な責任」。
会社内で事件が起きた場合に責任者が問われる問題、「民事的な責任」。
これによって、本人が命を落とすという損害があるわけですし、ご遺族も悲しい気持ちになるという慰謝料があるわけです。
他にもいろんな損害がある。
この損害に対する損害賠償責任、民事的な責任というのが大きく分けて二つに分かれるんですね。
例えば、雇い主ね。
法人だったら法人、個人だったらその雇ってる社長とかになるんだけども、「この雇い主が責任を負うかどうか?」。
皆さん、どう思います?

当然、職場内で起こったんだから会社も何らかの責任を負えよ
という気持ちの人もいれば

いやいや、そんな職場で起こったことを全部会社が防げるわけないじゃん。
会社が責任取るのおかしいと思う
という人もいると思います。
どっちなんでしょうね。皆さんね。
これはね、実はちゃんとした考え方があるんですね。
まず、「刑事的な責任」に関して、会社が責任を取るかどうかの考え方。
「刑事的な責任」の場合、これは刑事責任って基本的には、その行為を行った人が責任を問われることになるんで、よっぽどこの会社がグルになって事件を起こしたとか、煽ったとか、そういうことがなければ、刑事責任を問われるってことはちょっと考えにくいです。
でも問題は「民事的な責任」。
会社が責任を取るかどうかの考え方、「民事的な責任」の場合。
損害賠償責任なんですね。
これは実は、会社・雇い主側が責任を負う場合っていうのがあります。
二つあります。
一つ目。
これは「業務に関連して事件が起こった場合」。
例えば、わかりやすいのは事件じゃなくて事故なんだけども、営業マンが営業車に乗ってわーっと運転した時に、つい居眠りしてしまって人を轢いてしまう。
そして大怪我をしてしまう。
場合によっては亡くなってしまうという場合に、責任を負うのはこの運転してた人間だけなのか?
これはね、会社の責任もあるわけです。
なぜかっていうと、「報償責任」という考え方。
これ、何かっていうとですね、「報償責任」という考え方。
会社っていうのは、この従業員を使って従業員が成果を上げれば、その利益は会社に帰属するよね。
でも、従業員が何かをミスして誰かに損害を与えてしまう、損害賠償義務が生じるっていう場合は、プラスも会社に帰属するんだから、マイナスも会社に帰属すべき。
なので、会社も損害賠償責任を負います。
こういう考え方なんですね。
今は過失の事故の話なんだけども、故意の場合もそうで、被害者、この職員さんに対して会社が本来はこの業務に関連して、例えば業務のトラブルがきっかけになって、加害者が被害者に暴力を振るったりとか、今回みたいに〇害してしまうってことがあれば、それは業務に含まれるものなので、だから会社が責任を負うってことはあり得るわけですね。
これは、例えば「業務時間内に行われたか?」とか、「場所はどこか?」とか、「原因は何だったか?」ということをいろいろ調査して明らかにして、
それで、人に暴力を振るったのは業務ではないんだけども、「業務の延長として発生してしまったものだよね」というふうに認定になれば、会社も損害賠償責任を負うってことになります。
でも、例えばきっかけはちょっとした業務上のぶつかり合いだったかもしれないけども、その後、関係ないことで恨みを募らせる。
さっきもあったように、例えば自分の好きな女性に対して「あいつ等、仲いいわ(怒)」みたいな、もう完全にこれ業務と関係ないわけじゃないですか。
こういう恨みつらみでその人を憎んで事件に至るというケースだと、これはもう会社の業務と関係ないので、その場合は会社が責任を負わないってことに原則なるわけですね。
今、「原則」って言ったこと、気になった人いると思うんですけども、それが二つ目なんです。
例外があります。
何かっていうとね、会社には「安全配慮義務」がある。
つまり、環境を整える義務です。
例えば、崩れかけてる建物の中でお仕事させるとなって、実際に何か地震か何かで落ちてきて、バンと怪我すると。
いや、それはそんな悪い環境に置いてた会社が悪いじゃん。
こうなるわけだから、それはまあちょっと極端かもしれないけども、ちゃんと安全な環境で働かせるという義務があるんですね。
何もなければね、分かんないですよ会社も。
でも、普段からこの加害者、後の加害者がね、「いつかやってやる」「いつか酷い目に合わせてやる」なんていうことを公言していて、この社長の耳に入ってもおかしくない。
まあ、実際に入ってたりも含めてね、そういうような状態であれば、積極的に情報を集めて、そしてそういうことが起こらないような環境を整える。
例えば、隣同士の人だったらこの一人を別の部署に異動させるとか、机を離すとか、あるいは別の支店に動かすのも含めて、
物理的な距離を離すということで接触機会を減らして、そしてそういう突発的な事件が起こってしまうのを防ぐ努力をする。
あるいは、間に入って話を聞いて、この感情的なぶつかり合いを解きほぐしていくことができるんじゃないかとかね。
そういうふうに会社が「もしかしたらこういう事件が起こるかも」ってことを予想できたんだったら、そしたら、それを精一杯防ぐ義務があるよね。
その加害者になりそうな人を捕まえて、ずっと抑えておくとか、ずっと監視しておく、こういう非現実的なことじゃなくて、
できる限りのことをしましょう。してなかったら責任を負いましょう。
これが「安全配慮義務違反」というもので、それが認められた場合には会社に損害賠償義務が生じることがあります。
ですから、今回の事件もね、いろんな報道がされていて、それが本当かどうか全然分からないから、現時点では何も断言できません。
何もできないけれども、もし会社が実際にそのトラブルが起こりそうっていう状況を把握しているか、あるいは把握してもおかしくないぐらい、みんなが知っていたというような状況だったということが、もし分かってくれば場合によっては、雇い主である法人が損害賠償義務を負うということはあり得ます。
だからね、捜査というのは基本的に刑事事件のための捜査だから

どういう噂が広まってたんだろう?
ってことまでは、捜査の対象にならないんですけども。
捜査の対象って、あくまで「なぜこういう〇人事件が起こったのか?」という、動機の部分というのが一番今回ね、大きくフィーチャーされると思うんですけども。
捜査の中でね、それが分かってきて、「これ業務に関係するな」ってことが分かるとか、
あるいは「業務に関係してない」ってことが分かってくれば、いろいろ調査をしていって、実際にそういう噂が広まったかどうかなんてことを、法人は把握した上で、損害賠償責任を負うかどうかということが分かってくるってことになるんですね。
ですから、この捜査の過程でね、動機を解明するために、その同僚なんかにもいろいろ話を聞いていくと思うんです。
その時に、

ああ、あいつこんなこと言ってましたよ

こんな状況でした
とか、いろんな証言が出てくると思うんですね。
それを後で法人側がもう一度聞き取りをして、そして「自分たちに責任があるのかどうか?」っていうのを判断されることだと思います。
もちろんね、裁判になればそれを裁判所が判断するということになるかと思います。
自首の法的効果とは?
ここでね、裁判とか捜査にも影響することなんだけども、「自首っていうのが成立するかどうか?」、これが一つの争点になるんですね。
自首って、皆さんのイメージではどういうものですか?
犯人が警察に出頭して、

私がやりました
これがなんとなくのイメージの自首なんでしょうけども。
これ、報道ではよく「出頭した」っていう言い方をしますよね。
じゃあ、出頭と自首は違うのか?
実は、法的には違うんです。
厳密にテレビがそれを意識して変えているかどうかは、僕は分かんないんだけども、法的な自首とそれ以外の出頭ってのは違うんでね。
法的な意味での自首っていうのは、それが成立すると、裁判の時に裁判官が罪を軽くすることができるんですね。
もちろん、しなくてもいいんだけども、裁判官は

自首があったな
ということであれば、事件によるんだけども、罪を軽くする方向で考える。
じゃあ、その法律にも書いてある自首っていうのは、どういうときに成立するのかっていうとですね。
これは実は、自首がどういった時に成立するのか。
警察に「私がやりました」って言ったらいいだけではなくて、その前提が要るんです。
その前提っていうのは、事件が発覚していない、もしくは発覚しているけれども犯人が分からない。
どちらかのケースです。
つまり、そういうのって犯人が「もう黙っとこ」ってすると、ずっと事件が解決しないまま、もしかすると長期化はあり得るわけですよね。
それを、犯人が出ていって「私がやりました」っていうことで、これまで隠れていた事件が発覚するかもしれないし、あるいは犯人がすぐ逮捕されて、そして事件の解決が早くなるかもしれない。
だから、それを評価して「自首」と言ってるんですね。
だから逆に言えば、事件は発覚しています。
そして、犯人もだいたい目星がついてます。
という時に、

これ以上逃げ回れないや……
って出ていったとしても、それは自首にはなりません。
普通の出頭ですよね。
裁判官も「自ら出てきた」ということを全く評価しないってわけじゃなくて、それは多少は評価します。
だって、いくら犯人が分かってるって言っても、ずっと雲隠れしていれば事件の解決は結局延びるわけですから。
だから、そういう意味では犯人が分かっていても出頭するって意味はあるんだけども。
そういう場合ってどうなのかな。
やっぱり追い詰められたから「もうこれ以上逃げられないよ」と思って、反省とは別に出て行くっていうケースも多いんじゃないかなと思う。
そうすると、実際それを法律上、減刑事由つまり罪を軽くする事由として認めるのは、ちょっと躊躇があるってこと。
法律上はそこは、自首と出頭を区別してるってことなんですね。
今回の事件はね、おそらく職場内で起こったってこともあって、当然犯人はこいつだってことは分かっていたはずなので。
後から警察署に出ていった。
それで解決は早くなったとは言え、自首とは成立しないんじゃないかなと思います。
ただね、「なぜ自首したのか?」なんてことは、捜査の対象になるんじゃないかなと思いますね。
このような事件の発生を防ぐためには
とは言いましてもね、今回は職場内での〇人事件という、非常に衝撃的な事件です。
というのもね、皆さんもこれをご覧になっている方で、会社勤めの方もおられると思うんですけども、自分の会社に知っている知り合いが突然、自分に対して凶行に及ぶということ。
普段、考えてないと思うんですよ。
でも、こんな事件があったってことになると

もしかすると……

おちおち仕事もできない
っていう、そんな状況になるかもしれないし。
例えば、自分のパートナーだったりの方がですね、自分は家にいるけれども、
パートナーの方が会社勤めで「何か不穏なこと言ってたな」「仲良くないな」って言っちゃってたってなると、もう不安で不安で堪らなくなっちゃいますよね。
だから、正直、他人事ではないんです。
この事件が起こった事務所だったり会社だったりするのが特別でね、こんな事件が起こってもおかしくないっていうような、そういうところじゃないから怖いんですよ。
今回の事件も含めてね、じゃあね、会社側、あるいは雇っている側として、こういう事件というのは防ぐことはできないのか?
100%防ぐっていうのは無理です。
これは無理だとしても、出来る限りその可能性を低めていくという、そういう努力はできないのか?
これはね、僕はできると思ってます。
結局ね、こういう事件って人間関係のトラブルの積み重ねで、どんどんどんどん積み重なっていく。
悪いものが淀んでいく。
これで発生するんで、突然発生するってのは少ないわけですよね。
だから、人間関係の悪化ということを如何に早く見つけるか。
そういうことになると思うんです。
本来はね、僕もうちの事務所の経営者だけども、経営者だったりとか経営陣が目を光らせて
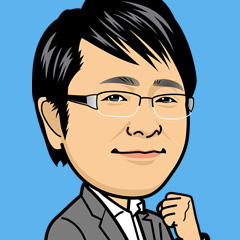
人間関係はどうかな?
何か不穏なことないかな?
ということを目を光らせる。
これが第一なんです。経営者の責任なんです。
だけど、はっきり言って、それを毎日ずっと事務所にいるわけじゃないし、会社にいるわけじゃないし。
そうすると、全員のことをずっと観察するっていうのも不可能だし。
あるいは、社長がいるってことで普段いがみ合っている二人がスンッと静かにしているかもしれないから。
社長とか経営者がそれを見るっていうのは、現実的には難しいかもしれない。
もちろん意識は重要だから、僕も気を使ってるけれども、でも完全にそれを見るというのは無理だと思うのね。
じゃあ、どうするのか?
これは単純で、かつ当たり前のことなんだけども、「他の社員、社員の目を使う」ってことなんです。
当然、プライベートでね、外で会ってる二人がトラブルになっても、これは分かんないんですよ。
でも

職場内であいつ等、何か険悪だな
っていうことは、少なくとも同僚は気づいてるんです。
ちょっと仲悪いぐらいだったら、そりゃ騒ぎません。
でも、やっぱり

これちょっと普通の関係じゃないぞ
何か普通の険悪さじゃないぞ
ちょっとまずいぞ
っていうことは、普段のこの周りの同僚っていうのは感じていることが多いんですね。
だから、いかにその声を経営者側に届ける。
そういう仕組みを作るかっていうところが重要になるんです。
例えばね、うちの事務所なんかで言うと、僕とそれぞれの個人が何かで繋がってて、何かあったら、

嵩原先生、実はあの人、今ちょっと落ち込んでるみたいですよ
気を使ってみてください
とかっていう話があったりして
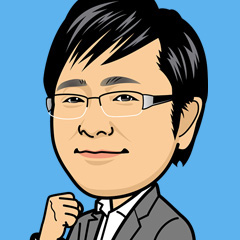
ああ、そうかそうか、ありがとう
ちょっと気を使ってみるようにするね
話を聞いてみるね
っていうことで、情報を集めてやるパターンであったりとか。
あるいは、嵩原に言いにくい。
だけど結構ベテランの事務員さんがいて、気のいいおっちゃんです。
「オウオウオウ!」みたいな感じのタイプの人なので、その人なら話しやすいってことで、そこで話が集まったりとか。
あるいは、女性の事務員さんがいるんですけども、その人に話が入ったりとか。
いろんなところでルートを使って、僕のところにできるだけ話が集まってくるように考えてます。
そうするとですね、「何かあったら嵩原にちょっと言っておこう」「耳に入れておこう」っていう意識を醸成することでですね、それでお互いがね、何かあった時に、これ別に告げ口じゃなくてね、いろんな情報が集まってくるから、対策が取れるわけですよ。
だから、そうやってると、うちはないけどもし二人がすごい険悪になって、ちょっとまずいぞって情報になれば、僕のところに伝わってくる可能性が非常に高いわけですよね。
でも、これって限界があるわけですよ。
顔を合わせて「嵩原に言えるわ」とか「あの人に言えるわ」っていう、個人的な繋がりで何とかなってるとこあるんだけども、おっきな会社になってくると、そういうわけにもいかないことがあると思うんです。
その場合に使うのは、皆さん分かると思うんですけども、「内部通報システム」。
これは、ただその会社にその窓口を置いた、「何かあったらここに電話してね」っていうことを置いただけでは全然意味がなくて、そんなことやるだけで満足したら、それは置かないのと一緒です。
重要なのは、それをどう活用するのか。
そこに連絡したら、こういう解決があった。
簡単なものでいいです。
例えば、

隣の人、いつも貧乏ゆすりしてて、ちょっと気になるんで席替えてほしいんです
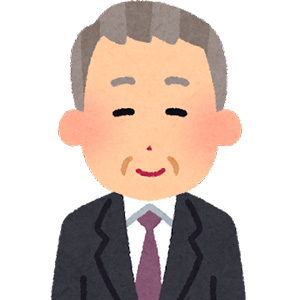
ああ、わかったわかった
この人を傷つけないように、別の理由で席変えるとか、何でもいい。
何か簡単なことでも解決してあげた、ということがあればですね、
「じゃあ、あれも言ってみよう」「これも言ってみよう」ってことになって、そして本当に大きな重大なものってものが伝わってくる。
だから、簡単なものを簡単に解決できるものと言うのかな、それを解決してあげる。
実例を見せてあげるということであったりとか。
普段から「こういう連絡あったので、すごく助かりました」「顧客のクレームあったんだけども、こういうことを先に聞いてたんで、すぐ対応できました」「ありがとう!」「誰とは言わないけれども」
っていうことを皆の前で褒めるとか。
そういうふうにして、「これ使っていいんだ!」っていう存在を何度も何度も社員さんに伝えるであるとか。
それによって、どう会社が良くなったのかっていうことを積極的に伝える。
そして、言ってくれた人に感謝を伝える。
こういうことをしておくとですね、皆が「使おうかな」という気になって連絡をしていく。
これは、電話なのか、メールなのかっていう形も大事だけども、それがきちっと運用できているということ。
これをするというのが、経営者だったりとか経営陣の責任じゃないかなと思います。
これができていれば、情報というのは集まってくるので、対応策というのもできてくる。
これはね、社員から気軽に相談を集めるのは、条件的に難しい会社もある。
簡単に言ってますけれども、会社のその業種であったりとか、社長がいつも会社にいるかとか、いないかとかですね。
あるいは、うちのベテラン事務員さんみたいな、すごく気のいいおっちゃんみたいな人材がいるかとかですね。
そういうような、いろんな事情がそれぞれの会社にあるわけですから、簡単に言ってますけども、それをこの会社ではどう実現していくのかっていうのは、僕も相談を受けるんでね、会社を見に行ったりして、いろいろ情報を集めたりしながら、「こんな感じがいいんじゃない」ってことを試しながらやっていく。
そして、その会社にカスタマイズした一番いい情報収集システムを作るというのを努力していく。
それを経営者が努力することで、少しでも何か不安の種を集めておく。
そしてそれを改善にやっていく。
こういう努力をしていくというのが、それが重要かなと思います。
そういう情報が集まってきたら、集めた情報をどう活用するのか。
誰がどういうふうに聞くかも重要。
すぐその当事者を呼んで、「おお、なんかこんな話聞いたけど、どう?」なんていう話を聞いたって意味がないので。
「あいつ、告げ口したな」と思いながら、「なんでもないです」って答えるだけなんでね。
誰がどういうふうに聞くのかっていうことも、実は重要で。
ここにも、ある意味テクニックだったりとか、気を使わないといけない部分というのはあります。
これも会社だったり、その社長とか経営者の個人的な性格であったりとか、人材であったりとかによって変わってくるのでね。
これも会社ごとにカスタマイズしていくことなんですけども。
そこに悩んで、そこの努力をしていくという姿勢を。
社長が努力している姿勢をね、それを社員に見せるということがですね、非常に重要じゃないかなと思っていて。
それを一生懸命実行します。
うちの事務所が完璧にできてるかっていうと、努力を続ける。
僕は一生懸命努力はしてるけども、完璧じゃないと思ってるから。
だから、努力を続けるという努力を続けてます。
はい(照)。
だから、そういう意味でね。
会社の経営者さん、見ておられる方、あるいは人事の方とかもおられるかもしれませんけども。
そういう方はですね、「いや、努力してるんだけど、うまくいかないんだよね」。
じゃあ、視点を変えていろんな人に相談してみるとかですね、うまくいっている会社のことを聞いてみるとか。
その運用面に目を向けてみてくれたらいいのかなと思ってます。
まとめ
今日はですね、某大手法律事務所で起こった非常に悲しい、悲惨な事件。
それを元にですね、そういう場合に会社がどのようなケースであれば責任を負うのか。
あるいは、こういう場合ってどういうところが争点になって。
あるいはですね、こういう事件の場合はどういうところが重要な情報として捜査されていくのか。
そして、こういう悲惨な事件を少しでも起こる可能性を低くしていくために企業側、会社側、経営者側はどんなことをしていけばいいのか。
ということについてお話しました。
みなさんも、何か「うちではこうしているよ」とか、「こういうところで悩んでるよ」ってことがありましたら、コメント欄にどしどしと寄せてください。
私もそれを参考にして、皆さんにどんどん発信していきます。
それでは、また。